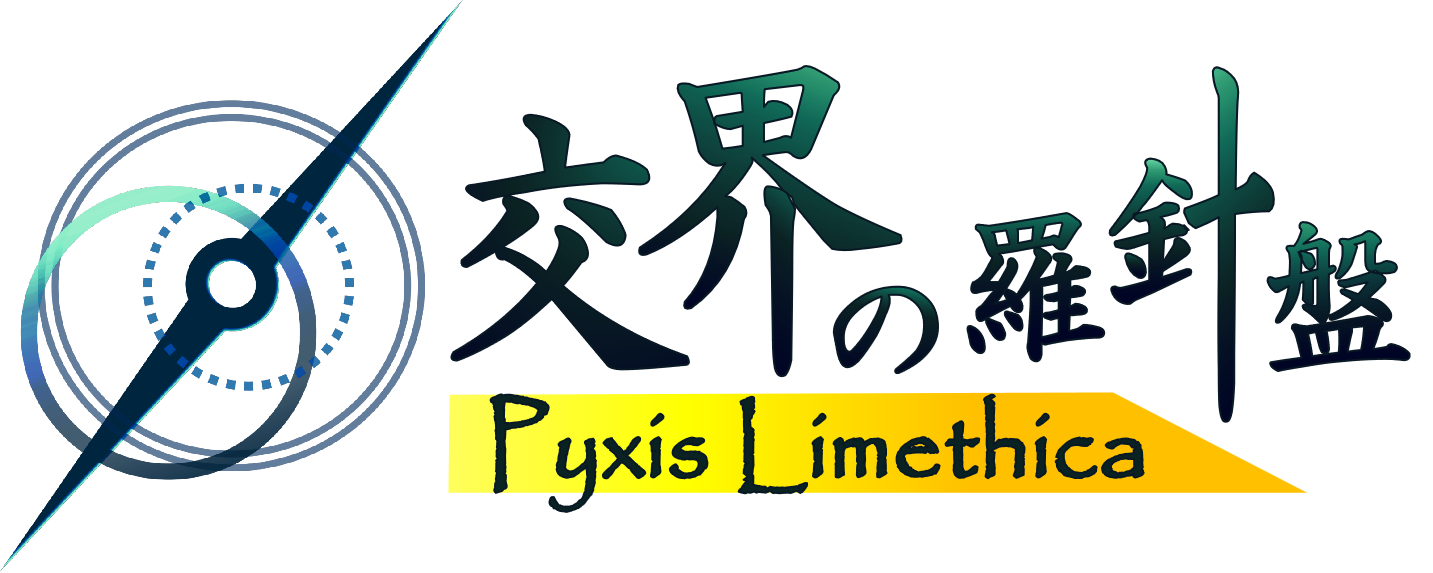※ 対訳に関する注記
各用語に付した対訳は、各言語圏で実際に見られる用例をもとに作成している。ただし、概念や語彙の対応関係は言語ごとに異なり、定訳が存在しない、あるいは複数の表現が併存している場合もある。ここに掲載する対訳はあくまで現時点での主要な例を示すものであり、今後の検討や対話を通じて変更・補足される可能性がある。言語の扱いに関する基本的な考え方については、言語の扱いに関するポリシーを参照されたい。
【あ】
アクターネットワーク理論
解説
韓:행위자 연결망 이론;행위자 네트워크 이론
中:行動者網絡理論;行动者网络理论
葡:Teoria Ator-Rede (TAR)
英:Actor-Network Theory (ANT)
行為や出来事は、単一の主体が意図的に生み出すものではなく、人間と他の諸事物のネットワークによって形づくられると考える理論および記述方法。主に科学技術社会論(STS)の文脈で、ブルーノ・ラトゥール、ミシェル・カロン、ジョン・ロウらの議論をもとに発展した。
ANTが考える行為能力(agency)とは、個々の主体が持つ性質ではなく、当の行為に関わる様々な存在(actant)の相互作用から立ち現れるものである。例えば、今日の食料生産は巨大企業が単独で設計しているというより、企業・消費者・動物・飼料作物・病原体・化学物質・工業機械・法制度など、多様な生物や無生物の性質と動態が作用し合うことで形成されている(いかに強大な権力を握っていようと、企業は動物や病原体や消費者の性質に影響されることを免れない)。そこでANTは、人間と他の諸事物をあらかじめ区別せず、どのような事物がどのように行為の連鎖に関与しているかを等しい注意で記述しようと試みる。
このアプローチが生まれた背景には、社会学で想定される「社会的なもの」の概念が、現象の説明を不充分なものにしているという意識があった。ラトゥールは、社会とは多様な存在が結び付くことで生成される集合体であると捉え、固定され限定された「社会的なもの」の枠組みを組み直す意図からANTを提唱した。それは規範的理論というよりも、既存の区分に頼らずに世界の連関を記述するための方法論であり、人間と他の諸事物からなるネットワークが、社会をどのように形成しているかを明らかにしようとする試みである。
ANTは従来的な行為能力の捉え方を揺さぶり、人間の脱中心化や社会と自然の二元論解体に寄与したと評される一方、主体性の有無や社会における力関係の存在を記述から度外視しているとの批判も向けられている。
関連概念:ポストヒューマニズム
【か】
解放神学
解説
韓:해방신학
中:解放神學;解放神学
葡:teologia da libertação
英:liberation theology
貧困者の視点からキリスト教神学を再解釈し、教会の社会的役割や不正な社会構造を問い直す神学運動。1960年代以降、グスタボ・グティエレス、エンリケ・デュッセル、レオナルド・ボフをはじめとするラテンアメリカの神学者らによって理論化された。
解放神学は、信仰を抽象的な教義や来世の救済に限定せず、現実の歴史過程における抑圧からの解放実践として捉える。キリスト教はいかに公正な社会の実現に関与しうるかという問いが、その思弁と実践の中核をなす。
グティエレスらによれば、貧困は自然発生的な不幸ではなく、植民地主義的な世界秩序や資本主義が生み出した社会的な不正である。物質的貧困は人間を非人間化する抑圧であり、聖書的には神に対する犯罪であると理解される。そのため、解放神学は階級闘争が現に存在することを踏まえ、貧困者とともに不正な社会構造の変革に関与することが、隣人愛の実践であると認識する。ここでは、異なる社会階級のあいだを往来し、抑圧の現実を可視化する聖職者の媒介的役割が重要な意味を持つ。
他方、解放神学は神にしたがう生き方としての清貧や、貧困者への連帯を選び取る意味での「貧しさ」を肯定的に評価する。「貧しい者は幸いである」(マタイによる福音書 5:3)や、「主は豊かであったのに、あなたがたのために貧しくなられた」(コリントの信徒への手紙 8:9)という言葉が、その神学的根拠とされる。
解放神学は社会主義思想と融合しつつ発達を遂げてきたが、そこには西洋哲学に由来する人間中心的なイデオロギーも混在していた。それに対し、レオナルド・ボフは解放神学にエコロジー的視点を導入することで、貧しい人々と地球はともに抑圧されていると論じた。
解放神学の系譜はラテンアメリカに始まりつつ、アジア、アフリカの神学やフェミニズム神学へと接続されていき、抑圧の現実に根ざした実践的神学として発展と拡張を続けている。
家父長制
☞ 父権制
環境倫理学
解説
韓:환경윤리학
中:環境倫理學;环境伦理学
葡:ética ambiental
英:environmental ethics
環境やそこに生息する生物に対し、人間がどのような根拠でどのような義務や責任を負うのかを考える倫理学の一分野。制度化された学問としてのそれは1970年代以降の欧米圏における環境保護運動を背景に発達したが、近年では世界各地の伝統に重要な環境保護思想が存在していたことが「再発見」され、その評価が高まっている。
環境倫理学はもともと生命倫理学の一環とされていたが、生命倫理学が人間生命の尊厳という主題に焦点を絞る傾向を強めたことから、やがて両分野は枝分かれの道をたどった。
環境倫理学は立場やフォーカスの違いによって、土地倫理やディープ・エコロジー、エコフェミニズム、社会主義エコロジーなどの諸分野を生んだが、その中で古くから論争の的となってきたのは、自然環境を人間による干渉から守ることを目指すべきなのか、自然環境を人間が賢明に利用することを認め、自然と人間の共生を図るべきなのかという点だった。前者を保存(preservation)、後者を保全(conservation)の立場という。今日の持続可能な社会づくりやSDGsの考え方は、基本的に保全の立場をとっているといえる。
その他、環境倫理学が扱う各論的主題としては、気候変動、生物多様性、持続可能性、土壌・水質・大気汚染といった身近なものから、食と環境、環境保全と不平等(環境正義)、未来世代への責任(世代間倫理)といった構造的なものまでが含まれる。
人間以外の存在を視野に入れる倫理学としては、環境倫理学のほかに動物倫理学もあるが、道徳的配慮の基準や範囲をめぐる考え方の違いから、両分野は協働とともに論争も重ねてきた。
関連概念:動物倫理学
交差性
解説
韓:교차성
中:交叉性
葡:interseccionalidade
英:intersectionality
複数の差別や力関係が絡み合って人々の経験を形づくっている実態を言い表わした概念。1970年代に活動したカンバヒー川共同体(Combahee River Collective)をはじめ、ブラック・フェミニズムの運動内で理論化されたのち、法学者キンバリー・クレンショーの論文において「交差性」と命名された。
例えば、黒人女性というアイデンティティを持つ人物は、人種差別と性差別を別個のものとして経験するのではなく、常に両者が溶け合った、どちらの差別とも分類しがたい複合的な逆境のもとに生きている。こうした状況は、差別や力関係を切り分けて捉える伝統的な社会正義の枠組みでは扱いきれないことが多かった。反人種差別の運動では、同じ人種に属する人々の中でも、男性の声が女性の声よりも優先され、反性差別の運動では、同じジェンダーに属する人々の中でも、白人の声が有色人種の声よりも優先される。よって、黒人かつ女性であるというように複合的な属性を持つ人々の経験は、いずれの運動においても周縁化される傾向がある。交差性の概念はこのような枠組みの限界を振り返り、抑圧の結び付きを明らかにすることで、社会正義の包摂性を高めるために提起された。今日では性と人種の交差だけでなく、身体条件・階級・出自・国籍・居住地など、様々な属性の交差とそれによる困難が注目されている。
批判的動物研究やポストヒューマニズムの文脈では、交差性の射程に「種」という属性も含められるべきこと、動物の境遇にも性や能力の違いをはじめ、さまざまな属性が関与していることなどが議論されてきた。
関連概念:フェミニズム
【さ】
自然の権利
解説
韓:자연의 권리;지구권
中:自然的權利;自然的权利
葡:Direitos da Natureza
英:Rights of Nature
人間の利害とは独立に、自然そのものの価値を守る法的権利。自然景観の保護をめぐる法的闘争の限界を踏まえ、20世紀後期に法学者クリストファー・ストーンが提唱したのち、ロデリック・ナッシュが体系化した。
従来の法体系では、人間に損害をおよぼさないかぎり、自然破壊事業を法的に訴え、阻止することができなかった。損害を受けない第三者は、当該事業に対する原告適格(法的な訴えを起こす資格)を持たないからである。そこでストーンは、自然物そのものに原告適格を認め、自然物の権利を代表して人々が法廷に立てる仕組みが必要であると論じた。
他方、ナッシュは歴史的観点から、権利主体が貴族から市民、そしてマイノリティへと広がっていったことを振り返り、現在から今後にかけては動物や植物や自然界へと権利の射程が広がっていくだろうと論じた。
日本ではかつて動物4種を原告とした通称「アマミノクロウサギ訴訟」が起こされたが、自然そのものは権利の客体であって主体にならないとの判決が下され、以後の類似訴訟も却下されている。しかし、ニュージーランドやエクアドルなどの国々では、先住民運動によって山や川や自然そのものに法的人格や権利が認められた例がみられる。また、韓国では現在、済州島の生きものと自然を守る目的から、実質的な自然の権利に当たる「生態法人(생태법인)」制度の導入が検討されている。
動物の権利は、まず哲学的・倫理学的な概念として理論化され、のちに法的な応用も少しずつ試みられてきたが、自然の権利は上記のように当初から法的な運用を目的として概念化されてきたことを特色とする。
資本主義
解説
韓:자본주의
中:資本主義;资本主义
葡:capitalismo
英:capitalism
生産活動に投じる元手を「資本」という。資本を投じて商品をつくり、商品を売って儲けを生み、儲けをさらなる資本として生産拡大に投じ、さらに大きな富を生む、といったプロセスでは、資本という形をとった「価値」が自己増殖していくことになる。このような資本の自己増殖運動に支えられた経済体制を資本主義という。簡略化すれば、資本主義とは「儲けが儲けを生むプロセス」に支えられた社会と定義できる。ドイツの経済哲学者カール・マルクスは、労働者が生み出す価値のうち賃金を超える部分(剰余価値)が資本として蓄積される仕組みがこのプロセスを支えていると考えた。
レスター・サローとロバート・ハイルブローナーなど、一部の経済学者によると、資本主義以前の社会では、人々は伝統や身分に縛られ、生まれによって職業や生活が強く規定されていた。市場はごく限定的で、土地や労働の本格的な売買もなかった。資本主義はそのような伝統秩序を解体し、人々に自由を与えるとともに競争社会で生き抜くことを求めた。
市場競争の中で沈まずにいるために、資本を持つ者は技術開発によって同業者を出し抜き、商品開発によって新たな市場を開拓していくことが使命となった。資本主義社会はこうして、無限の拡張・成長と、あらゆるものの商品化を特徴とする体制へと育ち、今日に至る。
資本主義のもとでは、価値を生む可能性のあるものは生物・無生物の区別を問わず商品システムに組み込まれる。いまや動物も自然も商品とされ、売買の対象となった。土地は「不動産」と化し、所有者の意向次第でどのようにも開発される。動物の身体は富を生む手段として扱われ、資本の投入によって生産性や効率性を高めるよう改変される。こうした現象は、資本主義の競争原理が働く社会の大きな特徴をなしている。
関連概念:植民地化
種差別
解説
韓:종차별
中:物種歧視;物种歧视
葡:especismo
英:speciesism
種の違いに応じて生物の価値に序列を設けること、または種の違いに応じて生物ごとの利害を異なる尺度で評価すること。特に、人間に属する者がみずからの利害を過大評価し、他の動物の利害を過小評価することを指して使われる。心理学者リチャード・ライダーによって発案され、倫理学者ピーター・シンガーの著書『動物の解放』を通して広く知られた。シンガーは種差別を「自分が属する種の成員にとって有利となり、他種の成員にとって不利となるバイアスもしくは偏った態度」と定義した。
「種」という生物学的概念の問題はさておき、種が異なれば何を利益または不利益とするかも異なってくるので、その違いに応じて適切な扱いも変わることは論を待たない。例えば、人間に参政権を認めることは利益となるが、豚や犬に同じ権利を認めても利益にならない。したがって人間のみに参政権を認め、豚や犬にそれを認めないことは、両者の利害を公平に評価したうえでの合理的な判断であり、差別にはならない。
それに対し、苦痛を負わせること、自由を奪うこと、芸を強いることなどは、人間にとっても他の動物にとっても不利益になる(逆にそのような加害を禁じることは、両者にとって同様の利益になる)。ところが今日の社会では、人間に正当な理由なくそれらの害をおよぼすことが問題視される一方、他の動物にそれらの害をおよぼすことは容認されている。例えば食肉産業やペット産業や娯楽産業が動物に行なっていることは、人間に対して行なえば重大な人権侵害となる。すなわち、動物産業では人間に対して行なってはならないことが、人間と同様の利害を経験する動物に対して公然と行なわれている。これは、人間と他の動物の利害が異なる尺度で評価されていること、人間の利害だけが重視され、他の動物の利害が無視または軽視されていることを物語っている。種差別という概念は、このような不合理を指摘するために用いられてきた。
なお、シンガーの定義にもあるように、種差別は長らく個々人の「偏見」や「態度」として理解されてきたが、社会学者のデビッド・ナイバートは差別が社会構造によって作られることを踏まえ、種差別をイデオロギー、すなわち社会の既成秩序を正当化する集団的な信念体系と捉え直した。
植民地化
解説
韓:식민화
中:殖民
葡:colonização
英:colonization
他者の領土を支配し、政治的・経済的利益のために現地の人々・土地・資源を体系的に搾取する過程。ヨーロッパ諸国は15世紀後半以降、南北アメリカ、アフリカ、オセアニアを中心に大規模な植民地支配を展開した。日本もまた、19世紀後期から20世紀中期にかけて帝国主義的拡張を進め、台湾や朝鮮半島をはじめ、東アジアおよび東南アジアの諸地域を支配下に置いた。
植民地化の主たる目的の一つは富の産出であり、プランテーション、鉱山開発、強制労働などを通じて、近代資本主義の成長を支えた。植民地支配は単なる軍事占領にとどまらず、法制度・教育・宗教・言語・知識体系を通じて現地社会を再編した。この過程で、現地の文化・言語・信仰は破壊または周縁化され、人々は「劣った存在」として非人間化された。のみならず、被植民者はしばしば支配者の視点を内面化し、みずからを「他者」として見ることを強いられた。
植民地化の歴史は過去のものとなっていない。形式的な独立後も、旧宗主国と旧植民地のあいだには新植民地主義、すなわち債務関係や経済協定、あるいは「開発援助」などを通じた不均衡な力関係と搾取関係が残存している。
関連概念:資本主義、ポストコロニアリズム
植民地性
解説
韓:식민성
中:殖民性
葡:colonialidade
英:coloniality
西洋近代を成立させると同時に、その不可視の暗部として存続してきた支配の原理を指す概念である。1980年代後半から90年代前半に、ペルーの社会学者アニバル・キハーノによって提唱されたのち、ウォルター・ミニョーロやマリア・ルゴネスらが担った「近代性/植民地性プロジェクト」の理論的中核として発展した。
ミニョーロによれば、西洋近代のナラティブ(物語)は、理性・進歩・文明といった価値を普遍的なものとして称揚する一方、それらを可能にした植民地化の暴力や搾取を不可視化してきた。植民地性とは、人間の価値、および文明や知識の正統性を序列化するこの論理を指す。
植民地主義は資本主義の発展や科学革命と結びつき、「創造」や「救済」の物語を描いてきたが、その陰では経済と知識の双方の領域で、植民地化された人々が使い捨ての存在として扱われてきた。奴隷貿易や人種差別的科学はその具体形にあたる。この意味で、植民地性なしに近代性は存在しえない。
植民地性は自然観にも深く関わっている。例えば、ラテンアメリカの先住民世界には、文化と自然が一体となったパチャママという概念があり、人間は自然の一部とされてきた。それに対し、西洋近代における自然は、「知は力なり」という言葉に象徴されるように、解明され支配されるべき対象と位置づけられる。植民地化とは、この西洋的自然観を導入し、他の存在理解を翻訳不能なものとして周縁化する過程でもあった。ミニョーロはこれを、植民地性による知と主体性の侵食とみる。
【た】
多種正義
解説
韓:다종 정의
中:多物種正義;多物种正义
葡:justiça multiespécies
英:multispecies justice
人間だけでなく、動物・植物・微生物・生態系など、多様な存在者の利益を正義の要請と捉える政治哲学。用語としては、ダナ・ハラウェイ『種が出会うとき』(2008)での使用が初期の例として知られ、その後、多種民族誌や環境正義の議論と結びつきながら理論化が進んだ。
多種正義は人間中心的な正義観の批判と、多種の関係網全体を考慮した社会変革の要求を使命とする。生態系の分断、動物の大量殺害、生息地の破壊などを、構造的・政治的な不正とみる点がその特徴をなす。
この立場は、正義や権利の概念を拡張し、意思決定の過程に多様な存在者の立場を組み込むことを試みる。例えば、生物多様性や他種の生存を考慮した都市計画、移動経路や生態系を保全するインフラ設計など、文明や生活様式の刷新がその課題となる。加えて、環境正義の系譜を受け継ぐ多種正義は、人間中心主義の見直しを図るだけにとどまらず、多様な人間集団の不均衡や脆弱性も視野に入れ、その克服をめざす。
こうしたことから、多種正義は批判的動物研究と重なるところが多いと考えられるが、前者は人間と他の動物以上の利害も勘案することに加え、「多種」という関係論的な枠組みを重視する点が独特といえる。
多種民族誌
解説
韓:다종 민족지
中:多物種民族誌;多物种民族志
葡:etnografia multiespécies
英:multispecies ethnography
人間を取り巻く生物や無生物を客体として扱ってきた人類学の伝統を見直し、人間以外の多様な主体の関係と共創に光を当てる民族誌(日本では「マルチスピーシーズ民族誌」と称されることが多い)。ポストヒューマニズムや科学技術社会論(STS)の議論を背景に、人類学者のエベン・カークセイやステファン・ヘルムライヒ、トム・ヴァン・ドゥーレンらが提唱し、学際分野として発達した。
従来の人類学(さらに人文学)は、人間以外の存在を人間生活の資源・象徴・背景と位置づけてきたが、多種民族誌は多様な存在者の絡まり合いを前景化し、人間や他の動物、植物、微生物、鉱物などが互いに影響を与え、互いを形成し合うプロセスを観察・記述することに努める。
この枠組みでは人間の主体性も人間以外のそれも、自律的な個体に帰属するものというより、さまざまな他者との関係の中で立ち現れるものと理解される。したがって、例えば飼い馴らしの歴史は、人間と他の動物(およびその他の関係する植物や微生物)のそれぞれが互いをつくり変えていったプロセスと捉えられる。
その研究の射程とアプローチからうかがい知れるように、多種民族誌における「種」は、生物学的なそれよりも外延が広く、安定的・自律的な「種」概念を改めるものとなっている。
関連概念:多種正義、ポストヒューマニズム
脱搾取
☞ ビーガニズム
脱植民地性理論
解説
韓:탈식민성 담론;탈식민주의 담론
中:解殖理論;去殖民化理论
葡:teoria decolonial
英:decolonial theory
帝国主義と民族解放運動の時代を経たのちもなお残存する植民地性に光を当て、その克服を目指す思想・実践運動。1990年代末以降、近代性/植民地性プロジェクトの担い手たちによって理論化された。
植民地主義批判としてはすでにポストコロニアリズムが存在していたが、脱植民地性理論は文明や知の枠組みそのものが西洋中心的に構築されてきた事実を問題化し、西洋理論を批判的に援用するだけでなく、知の出発点を南側諸地域の歴史経験や認識論へと移行させることをめざす。
近代性に内在する普遍主義的・二元論的認識論のもとで、非西洋世界は「劣等」「未開」「野蛮」と位置づけられ、その知や世界理解は周縁化されてきた。言語の領域にも同様の序列構造が存在し、西洋諸語は理論や知識を生産する言語として特権化される一方、非西洋の言語は文化や伝承を担うものにすぎないと暗にみなされてきた。
脱植民地性理論は、人種主義・父権制・理性崇拝・西洋的な神の概念などが絡み合った植民地性の構造を批判的に解体し、「異なる近代」ではなく「近代とは異なる選択肢」を構想する。単一的で資本主義的な世界秩序に代わり、複数の中心と複数の知が共存する非資本主義的な世界の可能性を探る点に、その核心がある。
関連概念:植民地化、植民地性、ポストコロニアリズム
動物解放論
解説
韓:동물 해방
中:動物解放;动物解放
葡:libertação animal
英:animal liberation
動物利用の廃絶を目指す思想の一つ。1970年代に哲学者ピーター・シンガーが著書『動物の解放』で用いた例が初出と思われる。シンガーによれば、解放運動とは恣意的な基準による差別や偏見をなくそうとする取り組みを指す。したがって動物を種差別から解放する取り組みは、「動物解放」の名にふさわしい。
動物解放論は動物の権利論と同一視されることも珍しくないが、前者は権利よりも平等を重視するニュアンスが強い(特に功利主義者のシンガーは権利概念の有効性を認めない)。例えば動物搾取に反対する理由を比較した場合、動物の権利論は「動物たちの内在的価値を権利の防壁によって守る」という考え方をするのに対し、シンガー流の動物解放論は「人間の扱いと他の動物の扱いにみられる不平等を正す」という考え方をする。
ただし、今日ではシンガーの文脈を離れ、人間解放と連続する正義という意味で動物解放という語が用いられることも多い。その場合、「動物解放」と「動物の権利」は実質的な同義語になっていると思われる。
動物の権利論
解説
韓:동물권
中:動物權利;动物权利
葡:Direitos Animais
英:animal rights
広義には、動物利用に反対する立場の総称。正確には、権利の概念を用い、動物を人間の手段とすることを禁じる思想。古くから存在するが、1983年に哲学者トム・レーガンが著書『動物の権利擁護論』で理論を体系化する。
レーガンによれば、動物たちは人間と同じく、みずからにとって意味のある主体的な生を生きており、ゆえに他者にとって価値があろうとなかろうと、その存在は動物たち自身にとって価値がある。この自分という存在の価値を内在的価値(inherent value)という。正義のもとでは、あらゆる存在がその持ち分に見合った等身大の扱いを受けなければならないため、主体的に生きる存在はその内在的価値を尊重されなければならない。そこで、内在的価値を他者による侵害から守るための権利が打ち立てられる。
動物を人間の道具や資源として利用する行為は、かれらの内在的価値を否定することになるため、動物の権利はそれらの行為を認めない。すなわち、動物の権利はあらゆる動物利用の廃絶と、抑圧される動物の救援を人々(道徳の意味を理解する者たち)に求める。
このように、権利とは利益を守るための「防壁」であり、それを人間以外の動物に敷衍(適用)したものが動物の権利となる。
動物福祉論
解説
韓:동물복지
中:動物福利;动物福利
葡:bem-estar animal
英:animal welfare
人間に利用される動物の苦痛をなくし、その福祉状態を向上させようとする考え方。1950~60年代頃に、動物の扱いをめぐる問題提起がなされたことから形成された。具体的なものとして、動物実験分野における「3つのR」や、畜産分野における「5つの自由」がある。3つのRは、実験で利用する動物の削減(Reduce)、代替(Replacement)、および動物の苦痛を減らす実験手法の洗練化(Refinement)を指す。5つの自由は、飢えと渇きからの自由、不快からの自由、痛み・外傷・病気からの自由、恐怖・苦悩からの自由、本来の行動がとれる自由を指す。
これらのアプローチから見て取れるように、動物福祉論は動物の産業利用そのものを否定せず、あくまで産業利用を前提としたうえで動物の苦痛を減らし、幸福状態を高めることを目指す。苦痛軽減や福祉向上を実現するには、動物の内面状態を客観的に評価することが求められるため、動物福祉論は一方で、動物の感覚や生態に関する科学研究を活性化した。
動物の内面状態に関する知見を深めたことは動物福祉論の成果といえるが、動物利用を否定しないその立場は動物の権利論と緊張関係にあり、この両者が相容れるか否かは論争の的となっている。
関連概念:動物の権利論
動物倫理学
解説
韓:동물 윤리학
中:動物倫理學;动物伦理学
葡:ética animal
英:animal ethics
動物の道徳的地位や、人間が動物に対して負う倫理的義務、ならびにそれらの根拠を探究する学問。これらの主題に関する思索は古代から存在したが、公式的な学術体系としての動物倫理学は、20世紀後期以降に動物解放論や動物の権利論が現れ、その妥当性をめぐる議論が活発になる中で育っていったといえる。
動物倫理学では上記の問題群を考える文脈で事例研究も盛んに行なわれており、そこでは肉食や動物実験から、動物園やサーカス、ペットの売買と飼育、野生動物への干渉まで、人間と他の動物の緊張関係を含むさまざまなテーマが扱われる。
かつては環境倫理学の一環に含まれることもあったが、 今日の動物倫理学は独立した領域へと育ち、時に環境倫理学の主流思想と緊張関係をきたすこともある。
【な】
内在的価値
解説
韓:본래적 가치;내재적 가치
中:固有價值;本有價值;天赋价值
葡:valor inerente
英:inherent value
道具的価値から区別される、その存在自体の価値。ドイツの哲学者イマヌエル・カントの哲学(特にその「尊厳」概念)をもとに、倫理学の中で定式化された。
存在の価値を考える際には、その存在が他者にとって有用か否かといった道具的な次元で測られる価値と、他者にとっての有用性に還元できないその存在自体の価値を区別する必要がある。前者を道具的価値、後者を内在的価値という。例えば、「他者の役に立たない人間に存在価値はない」という思想は、人間に道具的価値しか認めない立場となる。一方、「他者にとって役に立つか立たないかに関係なく、人間はただ存在しているだけで一定の価値がある」と考える立場は、人間に内在的価値を認める立場となる。
現在問題になっているのは、動植物や無生物のような人間以外の存在に内在的価値があるのか、そうだとしたらどこまでの存在にそれがあるのかという問題である。動物倫理学は、動物に道具的価値しか認めてこなかった伝統を批判し、動物の内在的価値を理論的に基礎づける作業に取り組んでいる。環境倫理学は自然物に関して同様の作業に取り組んでいる。
人間主義
☞ ヒューマニズム
人間中心主義
解説
韓:인간중심주의
中:人類中心主義;人类中心主义
葡:antropocentrismo
英:anthropocentrism
人間という存在に最大の価値を置き、人間の独断や目的にしたがって他のあらゆる存在の価値と扱い方を決める思想。その原型は有史以来存在すると思われるが、古代ギリシャ哲学やユダヤ・キリスト教思想において明瞭な形をとった。古代思想は「神中心的」な世界観に則っており、人間中心的な世界観はルネサンス以降の西洋社会において現れたとする議論もあるが、神中心の世界観においても人間は神の似姿かつ存在の頂点とされており、いずれにせよ「神」という形而上学的概念自体が人間の創作物である以上、ルネサンス以前の世界観も実際には人間中心主義だったといえる。「人間中心主義」という語の初出は不明であるが、環境保護思想の発達に伴い、この立場を批判する文脈でさかんに用いられだした。
人間の独自性や固有性は客観的事実として存在するので、それに着目すること自体は人間中心主義にならない。しかし、人間の独自性や固有性を尺度に、他の存在の価値や優劣を決める態度は人間中心主義となる。
人間中心主義は、人間以外の存在に一切の価値を認めないとはかぎらない。むしろそれは多くの場合、人間以外の存在に道具的価値(人間にとっての有用性)しか認めないことを特徴とする。すなわち、この思想のもとでは、あらゆる存在の価値が人間の利益や関心に従属する。例えば、環境保全の議論ではしばしば「このまま環境破壊が進めば私たちの生活が脅かされる」といった主張が現れるが、これは「人間を守るために環境を守る必要がある」という論理構造になっている点で、環境の価値を人間の利益に従属させており、一種の人間中心主義に陥っているとみることができる。
これに対し、人間以外の存在に道具的価値とは異なる固有の存在価値(内在的価値)を認める立場があり、それらは生命中心主義や多種正義、動物の権利論、ディープエコロジーなど、多様な枠組みを形づくっている。
【は】
ビーガニズム
解説
韓:비거니즘;탈육식
中:純素主義;纯素主义
葡:veganismo
英:veganism
あらゆる動物利用への加担を拒む哲学と生活実践。ビーガニズムの実践者をビーガンという。1940年代にイギリスのビーガン協会によって提唱され、のちに定義が整えられた。今日の公式的な定義によると、ビーガニズムとは「衣食その他、あらゆる目的による動物の搾取と虐待を、現実的で可能なかぎり暮らしから一掃しようと努め、ひいては人間・動物・環境のために、動物を使わない代替選択肢の開発と利用を促す哲学と生き方」を指す。
具体的には、肉・乳・卵・魚介類・蜂蜜などの動物性食品、皮革・羊毛・羽毛・毛皮・絹などの動物性衣類、動物園・水族館・競馬場などの動物娯楽、および動物成分を含む製品や動物実験を経て開発された製品を避けることが、ビーガンの実践となる。
もっとも、今日の社会では動物利用を完全に避けることが難しいため、ビーガニズムは「可能なかぎり」の実践を求める。可能と不可能の境がどこにあるかはビーガンのあいだでも意見が分かれるものの、代わりの選択肢があるか否かが一つの目安とされることが多い。例えば動物実験を経てつくられた製品を避けることは基本原則であるが、医薬品に関しては動物実験なしで開発されたものがほぼ存在しない。したがって、健康な生活に必要な限りでの医薬品利用については、現状致し方なしとされるのが一般的である。ただしもちろん、その現状はビーガニズムの倫理観に反するため、ビーガンは動物の犠牲を伴わない医薬品開発を支持する。
批判的動物研究
解説
韓:비판적 동물 연구
中:批判性動物研究;批判性动物研究
葡:Estudos Críticos Animais
英:Critical Animal Studies (CAS)
動物に対する抑圧の問い直しに始まり、あらゆる支配構造の解体をめざす急進的・学際的な研究領域。動物研究や人間動物関係学と呼ばれる分野の悪傾向を乗り越えるべく、2000年代初頭、社会主義者、無政府主義者、エコフェミニストなどの運動家や研究者によって形成された。
批判的動物研究の創始者たちによると、人間と他の動物の関係を考える従来の学術研究は、往々にして人間社会における動物たちの逆境を脇に置き、政治的に無難な議論へと流れる傾向があった。しかし、抑圧が存在する状況で「中立」を装う態度は、結果として抑圧を容認し、さらには強化することにつながる。そこで批判的動物研究は、見かけ上の客観性や見かけ上の政治的中立を排し、抑圧をなくすための研究、解放に資する理論構築をめざす。
現実に根ざした学問体系を築くには、学界と市井の境や専門領域の境を越える協働が不可欠であり、そのために研究者・活動家・市民・非営利組織などの人々が、建設的な対話を通して新たな知識や制度を形づくっていくプロセスが重要となる。また、研究者自身が社会を離れた「象牙の塔」に閉じこもらず、積極的に政治運動に参与し、ビーガニズムなどの倫理を実践することも要求される。
人間と他の動物の関係をめぐる倫理的探究としては動物倫理学があり、批判的動物研究もその理論を大きな基盤とする。しかし、動物倫理学が主として人間以外の動物に対する個人の道徳的な義務や責任を考察の主題としてきたのに対し、批判的動物研究は動物や人間の抑圧を生み出す社会構造へと視野を広げる。のみならず、その体系では動物・人間・自然の抑圧が構造的に絡み合っているという認識のもと、社会システムの変革による総合的解放が最重要課題と位置づけられる。
関連概念:動物倫理学
ヒューマニズム
解説
韓:휴머니즘;인본주의;인간주의
中:人類主義;人类主义
葡:humanismo
英:humanism
人間の能力や可能性を賛美し、外的な束縛や抑圧から人間を解放する思想。ギリシャ以来の西洋哲学を背景として、ルネサンス期以降に発達した。
もともとは神中心の世界観や非科学的な迷信、あるいは国家権力による抑圧からの解放を求める哲学であったが、やがてヒューマニズムはその考え方をもとに、個人の自由な自己実現を目指す個人主義や自由主義、理性への信頼に根差す科学合理主義へと結び付いた。
人間の尊厳を基礎づけるヒューマニズムの哲学は、動物の道徳的地位を再考するうえでも有用であるため、動物倫理学の参照点にもされてきたが、その枠組みはあくまで人間の能力や条件を基準にするため、人間からかけ離れた存在の倫理を考えるには適さない部分もあった。そのため今日では、ヒューマニズムの限界を乗り超えるべく、ポストヒューマニズムの思想が注目を集めつつある。
関連概念:ポストヒューマニズム
フェミニズム
解説
韓:페미니즘;여성주의
中:女性主義;女性主义
葡:feminismo
英:feminism
性差別を批判し、女性や性的マイノリティの権利と尊厳を確立しようとする思想および社会運動。単一の理論ではなく、歴史的背景や問題意識の違いに応じて、多様な立場や流派を含んでいる。
思想的・哲学的な区分としては、法的平等や選択の自由を重視するリベラル・フェミニズム、日常生活に埋め込まれた性差別的な支配構造(父権制ないし家父長制)を批判するラディカル・フェミニズム、性差別と階級・労働の関係を分析するマルクス主義フェミニズム、女性支配と自然・動物支配の結びつきを分析するエコフェミニズム、人種や植民地性とジェンダー抑圧の交差に光を当てるブラック・フェミニズムやポストコロニアル・フェミニズムなどがある。
歴史的には、フェミニズムは一般に「波(wave)」という区分で整理され、女性参政権の獲得を中心とした第一波フェミニズム、家庭や職場、性的関係における構造的な性差別を批判した第二波フェミニズム、ジェンダーと人種・階級・国籍などの交差性を重視した第三波フェミニズム、そしてデジタル空間での発信や抗議を特徴とする第四波フェミニズムに分かれる。ただし、これらの区分は重なり合いを含み、単純な世代交代を意味するものではない。
フェミニズムは発祥当初から、他の社会運動と密接に結びついてきた。第一波フェミニズムを担った人々の多くは奴隷制廃止運動に関わり、動物実験や動物虐待に反対する活動にも積極的に加わった。第二波ラディカル・フェミニズムやその系譜を受け継ぐ議論では、女性を抑圧する客体化や生殖統制の原理が動物搾取の根幹にもなっていることが指摘されてきた。
エコフェミニズムは、女性支配と自然・動物支配が同一の原理にもとづいていると捉え、「人間/動物」「男性/女性」「理性/感情」などの二元論が相互に結びついて支配の論理を形づくっていることを明らかにした。
加えて、フェミニズムは従来の社会正義論や倫理学が男性中心的な視点で構築されてきたことを批判し、環境倫理学におけるジェンダー視点の欠如や、動物倫理学における感情やケアの軽視にも問題提起を行なってきた。
このように、フェミニズムは性差別の打倒にとどまらず、権力関係、知の構造、倫理の前提そのものを問い直す視点を提供してきた枠組みであり、社会正義の理論と実践に持続的な刷新をもたらしている。
父権制
解説
韓:부권제;가부장제
中:父權制;家父長制
葡:patriarcado
英:patriarchy
男性が権力を握り、女性や女性的存在が従属状態に置かれる社会・政治的な構造。人類学や社会学の用語として成立したのち、ケイト・ミレットをはじめとする第二波フェミニズムの理論家たちによって、現代社会を批判的に分析する概念へと転用された。
この言葉はもともと、人類学や社会学において、家長や族長と呼ばれる年長の男性(patriarch)が統治権や支配権を握る政治体制を意味していた。フェミニスト歴史学者のゲルダ・ラーナーらによれば、その起源は、農耕・牧畜の始まりとともに男性が財産の所有・管理権を掌握し、母系的な親族構造から父系家族への転換が進んだことにあるとされる。この過程で、男性は血族や家系に所属する主体となり、女性は男性のもとに所属させられる者と位置づけられることになった。
1960~70年代に台頭した第二波フェミニズムは、このような歴史的に形成された権力関係が、現代の一般社会にも形を変えて存続していると捉え、父権制を男性支配型の社会・政治体制一般を指す概念として再定義した。この立場では、父権制は特定の男性個人の意識や性格の問題にとどまらず、法制度・労働慣行・家族規範・言語・知識体系などに組み込まれた構造的な支配関係として理解される。
第二波フェミニズムの重要な貢献は、家庭や親密圏のような個人的とされてきた領域もまた政治的であるとし、結婚・家事・性表現といった一見「自由な選択」に見える行為の背後にも、父権制の構造的力学が作用していることを明らかにした点にある。
ただし、父権制は単一で普遍的な制度ではなく、歴史的・文化的・地域的条件によって異なる形をとる。現代フェミニズムでは、父権制を固定的な「男性対女性」の対立として捉えることへの批判もなされており、人種・階級・植民地性・セクシュアリティなどとの交差において、この概念を再検討する動きも活発化している。
エコフェミニズムや菜食フェミニズムの議論では、父権制が財産所有の論理を通じ、女性・動物・土地の同時支配を定着させてきたことや、父権制と牧畜文化の根底に共通の支配イデオロギーが存在することに注目が集まってきた。これらの議論は、人間社会内部の議論を超え、父権制を自然や他生命の支配と結びついた構造として捉え直す視座を提供している。
ポストコロニアリズム
解説
韓:포스트식민주의
中:後殖民主義;后殖民主义
葡:pós-colonialismo
英:postcolonialism
植民地主義や帝国主義が残した政治的・経済的・文化的影響を批判的に分析する研究領域。1960年代以降の脱植民地化の過程を背景に、1970〜80年代にかけて批判理論やポスト構造主義の影響を受けつつ発展した。代表的な理論家には、フランツ・ファノン、エドワード・サイード、ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク、ホミ・K・バーバがいる。また、フェミニズムとの接点も重要であり、チャンドラー・タルパデー・モーハンティー、リーラ・ガンディー、サラ・アーメッドらはポストコロニアル・フェミニズムを形成している。
ポストコロニアリズムは、抑圧・周縁化されてきた人々の視点から世界を語り直そうとすることを重要な特徴とする。そのため、それは単一の理論体系ではなく、時に対立を含む多様な理論的立場の集合体として存在する。主要なテーマには、新植民地主義の構造、「中心/周縁」「私たち/かれら」の二元論、非人間化の論理、脱植民地化とナショナリズムの緊張関係、ジェンダー・階級・植民地性の交差などが含まれる。
さらに近年では、ポストヒューマニズムや批判的動物研究との交流を通し、植民地支配における「動物性」概念の利用、人種差別と種差別の連関、植民地化に伴う動物搾取や生息地破壊など、人間の抑圧と他生命の抑圧の絡み合いも主題化されつつある。
ただし、ポストコロニアリズムをめぐっては、植民地主義の終わりを示唆する「ポスト(後)」という接頭辞を用いている点や、欧米系の理論を(批判的・戦略的にであれ)援用している点などが争点となっており、西洋中心的な知と世界のあり方をより根本的に見直す領域として、脱植民地性理論がラテンアメリカを中心に発達してきた。
ポストヒューマニズム
解説
韓:포스트휴머니즘
中:後人類主義;后人类主义
葡:pós-humanismo
英:posthumanism
「人間」という概念を再考し、ひいては特異な「人間」概念に依拠してきた知識体系の再構成を目指す学術的運動。ポストモダニズムやポスト構造主義と呼ばれる思想潮流においてヒューマニズムの前提が問い直されてきたことを背景としつつ、20世紀以降に発達した。
ヒューマニズム台頭後の西洋思想では、人間は他の生命と本質的に異なる存在、かつ自然界から独立した存在とみなされてきた。例えば人間は理性を具え、言語を用い、社会を作り、歴史を歩むなどの点で、他の動物とは一線を画すとされる(ヒューマニズムではそれが人間の尊厳の根拠とされる)。そして西洋文化圏の知識体系はこの認識を前提に形作られてきた。
しかし、世界に関する知識が増える中で、人間と他の生物の共通性や連続性が明らかになり、人間の身体・文化・社会・歴史などがさまざまな地球存在との相互的な関わりの中で形作られてきたことも浮き彫りになった。加えて、人間の専売特許とされてきた理性や言語や社会が動物界に広くみられることも判明し、推理や言語を駆使する人工知能なども登場したことで、人間を特別視する根拠は瓦解を迎えた。
こうした背景のもと、西洋的ヒューマニズムの人間観と、それを前提とする知識体系は修正を迫られることになり、ヒューマニズムを乗り越える思考の実践として、ポストヒューマニズムが形づくられた。
関連概念:アクターネットワーク理論、ヒューマニズム
【ま】
マルチスピーシーズ民族誌
☞ 多種民族誌